技術資料
やわらかサイエンス
毒々しい話:フグ毒(後編)
そもそも何故こんな強力な毒をフグは持つ必要があるのでしょう。生物が毒をもつ理由は、外敵から自分の身を守るため、エサを捕るため等です。ではフグはどうでしょうか。
フグと毒
フグの中でもクサフグ等の体表(皮膚)に毒をもつ種は、外敵に遭遇すると膨らんで威嚇するとともに皮からテトロドトキシンを放出します。放出されたテトロドトキシンは周囲の海水で希釈されるので外敵が一気に死亡することはありませんが、一般の無毒な魚は味覚器官でごく低レベルのテトロドトキシンを感知できます。これによりフグを不味いものとして認識し、捕食を忌避すると推察されています。多くのフグは、やはり外敵から身を守るために毒があると言われているみたいです。しかし、フグの中には体表に微量(弱毒)程度しか毒を持っていない種もいます。これらは肝臓や卵巣、腸管などの内臓により強毒を持っている種のようです。もし外敵に襲われたとして、撃退のために自らの内臓を差し出すとなると、命を落とす可能性が高く感じます。どうやらこの毒は単に身を守るだけではないようです。
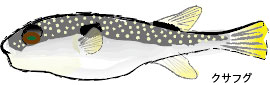
毒物として強く知られるテトロドトキシンですが、実は毒以外の機能としてはフェロモンとしての役割があるのではないかと考えられています。実際に、フグがフグ毒に引き寄せられていることやフグ毒を嗅覚で感知していることが報告されています。クサフグは大潮の満潮時に波打ち際の磯の上に上陸し、集団で産卵を行っています。これは一度に沢山の個体が産卵場に集まる方が効率よく子孫を残すために望ましいからとのこと。そのため、体表から放出されたフグ毒をかぎつけて集まっているのかもしれない事から、もしかしたらフグ毒は集合フェロモンとしても機能しているのではないか、とも考えられているみたいです。面白いですね。
さて次に疑問としてあげられそうなのは、フグがどうやって毒を得たのかでしょうか。フグが保有するテトロドトキシンの量はフグ自ら毒を作り出した、とは言えない程大きな個体差があります。また、1964年にテトロドトキシンの分子構造が明らかにされて以降、ほかの多様な生物種(イモリ、カエル、巻貝類など)からフグ毒が検出される事が明らかにされています。これらから、フグが自ら毒を作り出していないと言われています。

ではどうやって毒を得たのかというと、細菌起源の食物連鎖からと考えられています。細菌から上位の生物に移行するにしたがってテトロドトキシンが生物濃縮されて、それらをフグが摂取、蓄積していると推察されています。孵化時から無毒の餌を用いて人口飼育するとフグは無毒になるのはテトロドトキシンの獲得は外因性だからという事です。
環境変化とフグ
フグは種類によって可食部が変わるのはご存じでしょうか?厚生労働省で公開しているフグの可食部に関しては大きく3つの部位に分けて書かれていますが、種によって食べられる所は異なります。そんなフグですが、近年どうやら温暖化の影響で雑種のフグが増えてきているようです。
雑種のフグが増えることによる問題は、毒の位置が不明になる事です。先ほども述べましたがフグは種類によって毒をもつ位置が変わります。そんなフグから生み出される雑種のフグですから、どこに毒があるか余計にわからなくなります。さらに毒が毒なものですから、まあいいか!では済まされず、雑種含む種類不明なフグは厳重に選別および排除が必要になってきます。ちなみに厚生労働省の通知(フグの衛生確保について)で認めた部位以外の販売、提供をした場合は食品衛生法に引っかかります。
雑種が増えているだけでなく、生息位置も変化してきています。現在フグの漁獲量のトップは北海道(2023年6月)ですが、かつては福岡県が漁獲量全国1位でした。こうしてみると、九州から北海道までとかなり移動しましたね。とはいえ、海水温が上がったのなら温度が適切な場所へ移動するしかないでしょうから何とも難しい問題です。
今回は「毒々しい話」と題して、フグの毒から環境問題までをお話しました。主題は毒のつもりでしたが、環境問題にまで話がいきましたね。環境問題のもたらすフグへの影響は食の観点から目が離せませんし、テトロドトキシンの研究の進展も楽しみです。

