技術資料
やわらかサイエンス
毒々しい話:フグ毒(前編)
大学の学部生時代に毒に関する授業を取りまして、その授業が大変面白く、専門科目とは別で色々調べては目を輝かせておりました。危険かつスリルのある話は、それ相応の恐怖と共に未知に対する興味も引き出す・・・といったところでしょうか。これが、吊り橋効果!?という冗談はさておき、個人差はあると思いますが私はこういう話が好きです。
今回は身近(?)にある、フグ毒に関するお話をしてみようと思います。

テトロドトキシン
食べるとおいしいフグではありますが、実は彼らには毒がある、というのは結構有名な話ではないでしょうか。日本ではフグを食す文化があり、時折フグによる食中毒を耳にする機会があるからです。食中毒とまではいかずともフグによるニュースはそれなりに世間を騒がせている気がします。また、日本では年間約30件のフグ毒中毒が発生し、患者数は約50名で数名が死亡しています。その原因の多くは釣り人や素人による家庭料理だとか。近年はコロナ禍などの影響で事例が減少したように感じますが、それでも数件報告が上がっているようです。これらのことから、一般の人がフグを捌いて食べる、というのは絶対に避けるべきですし、魚市場ではフグを捌く免許のない人へ、処置をしていないフグを売るなんて事はありえません。
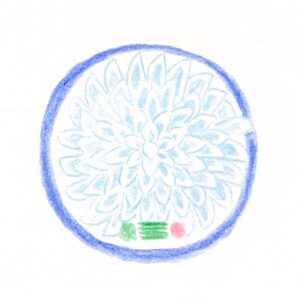
さて、世間を騒がせるフグ毒の正体は一体何だ?と言いますと、『テトロドトキシン』という神経毒です。神経の名を冠する毒ですから、神経系に影響を与えてきます。簡単に説明すると、テトロドトキシンは体内に取り込まれると神経細胞や筋肉細胞のナトリウムチャンネルに結合し、作用することで神経伝達を阻害します。これによって呼吸に関わる筋肉の機能が失われ、最悪の場合は窒息死します。ちなみに心筋はこの毒に対する耐性を持っているようで、心臓は働き続けるのだそうです。
現在この毒に対する解毒剤や特効薬は存在しません。では摂取したら最後、手立てなく死に瀕してしまうのか、と問われたら実はそうとも限りません。ここで人間がテトロドトキシンによる中毒を起こした時の致死時間を見てみましょう。まず食後の20分~3時間で唇や舌先のしびれが現れます。ここから四肢のしびれ、知覚麻痺、言語障害そして呼吸困難を起こし、最悪の場合は呼吸麻痺で死亡します。この最悪の場合による致死時間は4~6時間が最も多く、長くても約8時間です。この時間を持ちこたえると急速に回復します。これはテトロドトキシンとナトリウムチャンネルの結合が可逆的なため、摂取してしまったテトロドトキシンが分解または排出されると生きながらえる事ができるからです。ちなみに、後遺症も残りません。やったね。つまり、致死量のテトロドトキシンを摂取してしまっても、呼吸障害をカバーできれば、確実とは言い切れませんが生存できる可能性が大きく上がるのです。とは言っても、人工呼吸器のある設備のしっかりした病院へ運び、毒を体外に排出するまでの苦労や時間を考えると摂取しないに越したことはありませんね。
付け加えておくと、テトロドトキシンの致死量は大体1~2mgです。比較になるかはわかりませんが、塩少々(親指と人差し指の指先で塩をつかんだ量)が約300mg~600mg程度だそうです。こう考えると、致死量に至るまで、かなり少ないと思いませんか?
前編では、フグの毒の正体を紹介しました。では、フグはなぜ毒を持つのでしょうか? そして環境の変化はフグにどんな影響を与えているのでしょうか?後編でその答えを探ります。
参考資料
1)厚生労働省 自然毒のリスクプロファイル
1-1)自然毒のリスクプロファイル:魚類:フグ毒
2)糸井史郎 『テトロドトキシンの生物学的意義とフグ毒中毒』栄研化学
3)荒川修 『フグの毒テトロドトキシン-保有生物やフグ食文化との興味深い関わり合い-』J-Stage
4)環境省 せとうちネット
瀬戸内海とわたしたち/CHAPTER.1 瀬戸内海はかけがえのない海/代表的な生きもの/フグ
5)国立科学博物館魚類研究室 魚さまざま/フグ毒
6)NHK NEWS WEB:地球温暖化「環境DNA」が映す魚たちの北上
※最終閲覧日 2024/9/26

